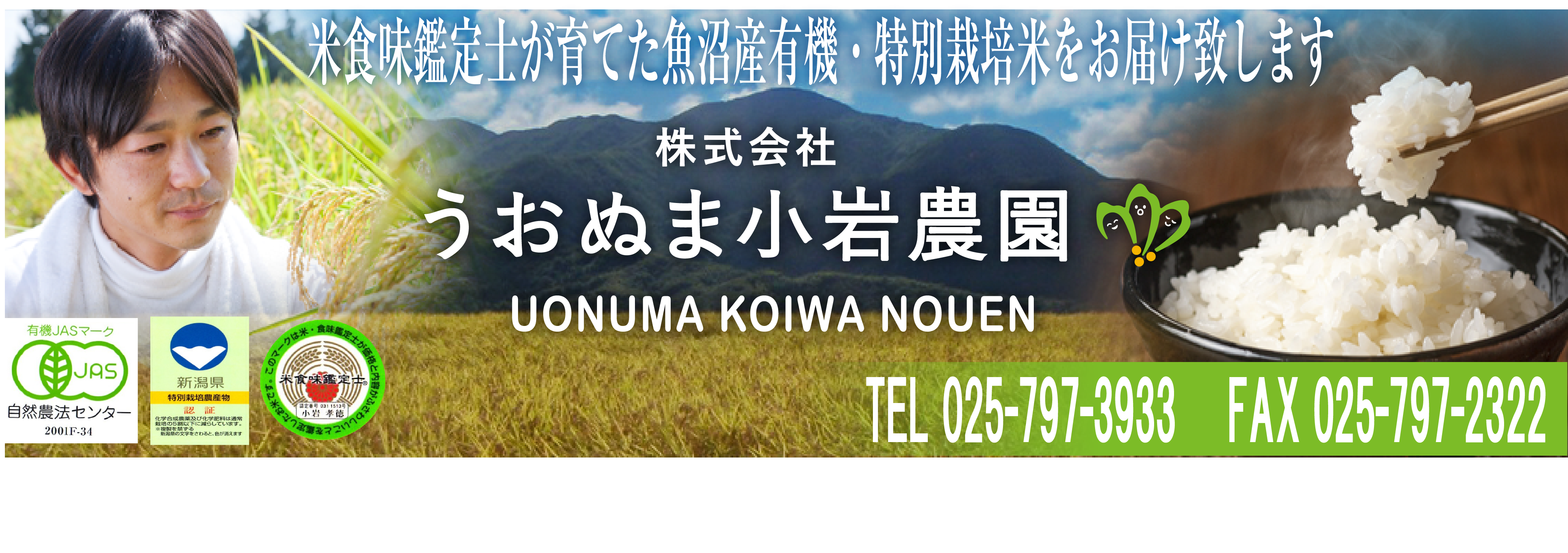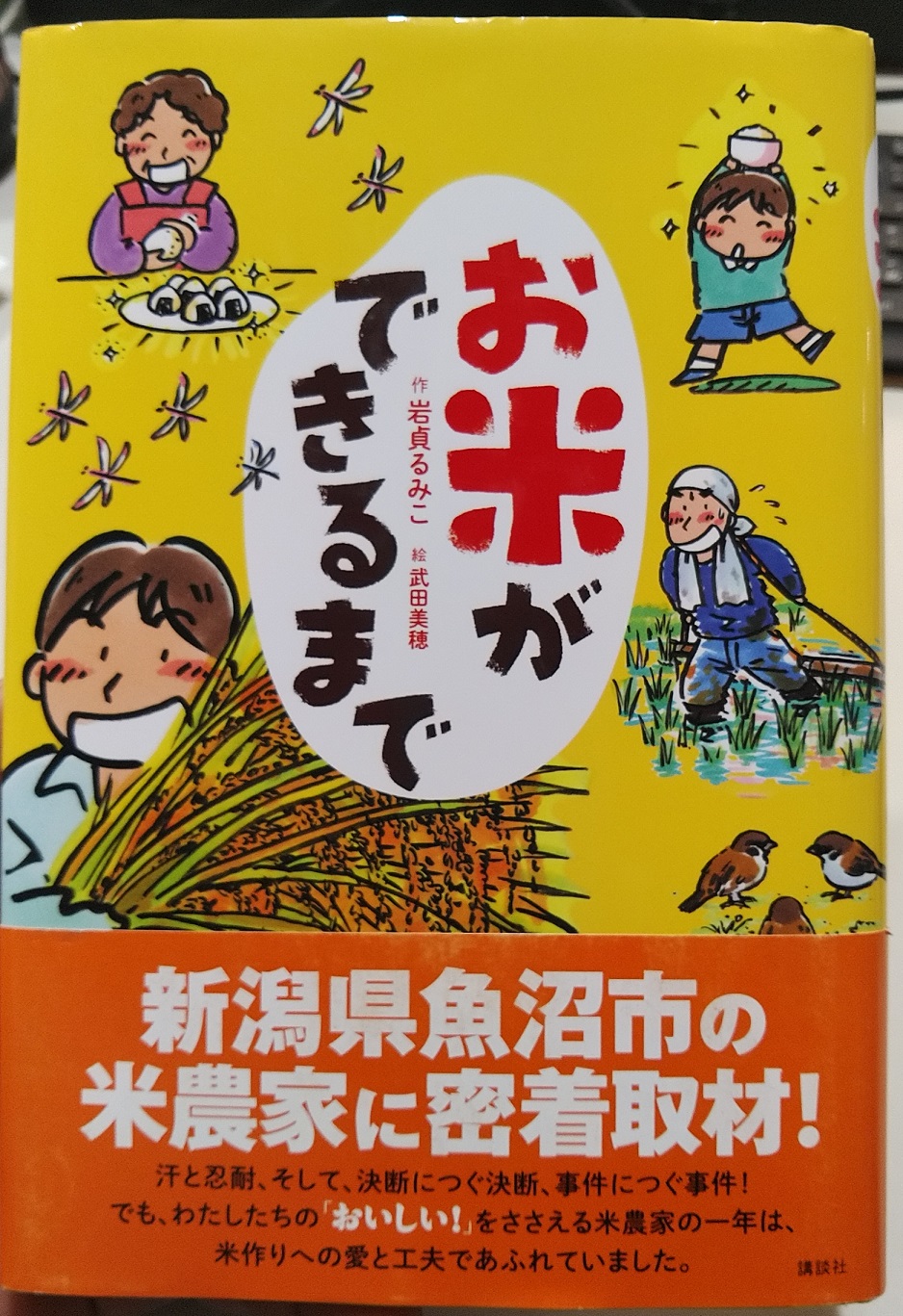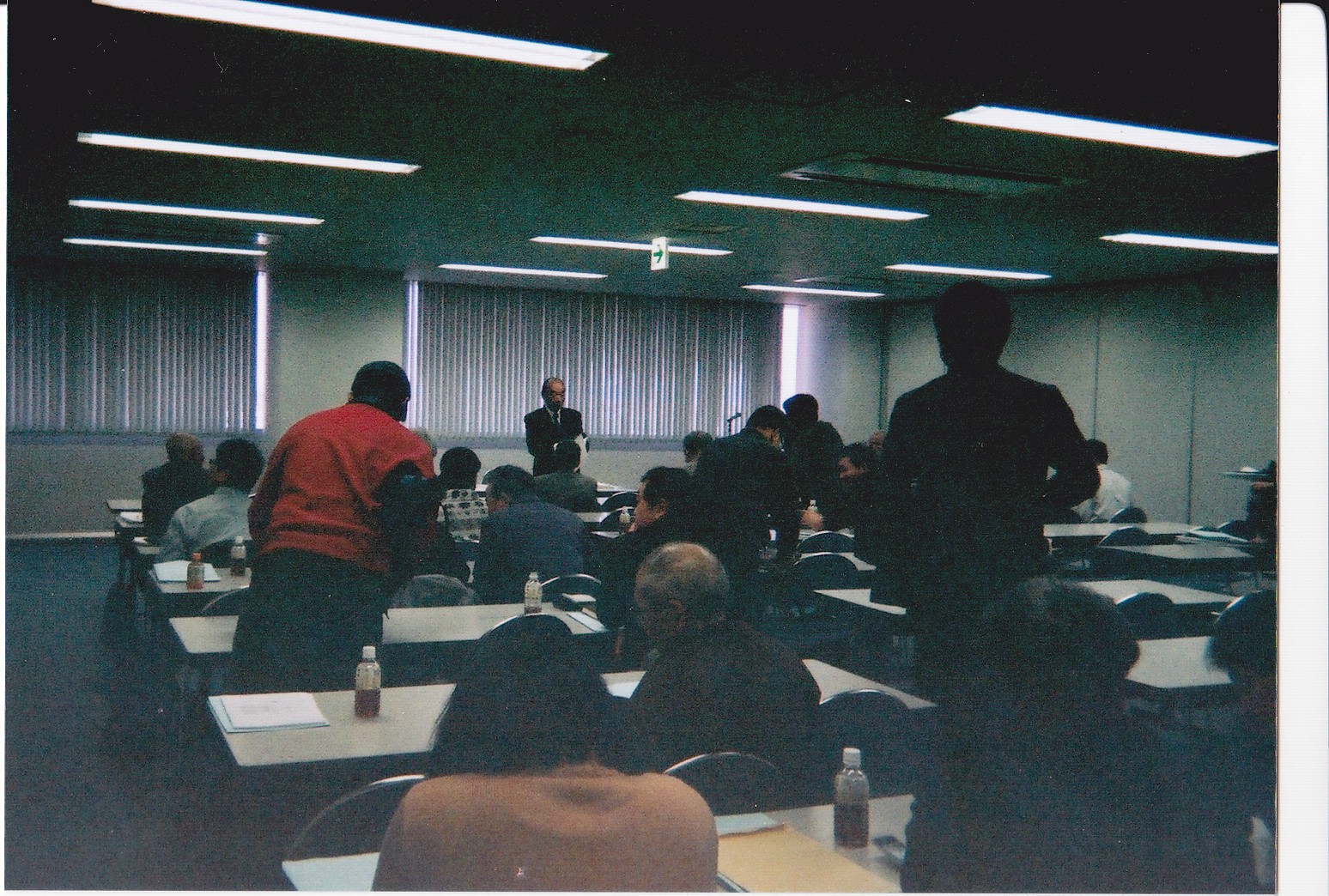2012.4.13
種籾をお湯に浸すと芽が出てきます。
この時酸素を同時に入れると、芽と根が出てきます。
種から白く出ているものの上が根で下が芽になります。
(芽が少し長いようです)
これを床に広げ、乾燥し、明日はいよいよ種まきです(*^_^*)
‘魚沼産コシヒカリ奮闘記’
ハウス作り
2012.4.11
雪を除雪機で強制的に飛ばして、やっと地面が見えてきたのでハウス作りの開始です。
この場所は3年目なのでハウス作りは楽に出来るようになりました。
しかし、以外と手間がかかるのは地面の整地です。
なぜなら高低差を3センチ以内にしなければならないからです。
うちは「プール育苗」といって水をいっぱい溜めた中で苗を育てているので、水が多いところと少ないところがあっては生育にムラができてしまいます。
「プール育苗」はずっと水に浸かっているので病気の発生が少なく、後の水やりの管理が楽ですが、この「整地作業」がとても大変です。
レーザーレベラーで計測しながら整地していくのですが、最初の年は地盤が安定しなかったせいか、1つのハウスに2日もかかってしまいました(>_<)
これが終わればひとまず安心です(^_^)v
次はいよいよ種まきです(*^_^*)